| Top Page > 同期演奏のヒントなど |
|
ライブ感を損なわない同期演奏をするためのヒントや同期音源制作のコツなど |
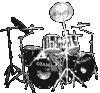
同期音源制作のヒントや、 同期演奏をライブっぽくする笑える一例など 同期してドラムを叩く感じをつかんでもらうために、スタジオ練習の感じを録音したものを一部アップしてみることにしてみました(笑)。 マイクのセッティングが面倒なので、ドラムの背後(自分の後ろ)にマイクを1本セッティングしているだけなので、今回はギターやボーカルの音は拾っていません。 同期音源のクリック・ベース・シンセはラインで繋いでいるので、それとドラムの音が一発録りされている感じになっています。 同期をしてドラム叩く場合のケーブルの繋ぎ方の一例などはこちらのページの下の方に載せています。 同期演奏用の音源の作り方の例 私が所属しているバンドでは、ベースが不在の為に、ベースとシンセを私自身がレコーディングして(私は別にベーシストではないので、かなりセコ技レコーディングでなんとか根性で慣れもしない5弦ベースを必死こいて録音しています/笑)、それに合わせて私がドラムを叩いているという感じですが、 同期音源のメディアは、あえてMDを選んでいます。 YAMAHAのMD4SというMTRで普通のMDを再生できるので使い勝手がよいのでMDにしています。出力時にパート毎にEQやバランスを細かく調整したい場合はハードディスクの方がよいでしょうが、MDでも充分同期用音源の制作・同期演奏は可能です。 まず、普通のMDはステレオトラックという事なので、 実質、左のチャンネルと右のチャンネルに分かれている2トラック音源という事になります。そして左右のチャンネルは、パンを振り切った状態で録音すれば出力時に完全に独立させる事が可能なので、 これを利用して同期音源のシンセとクリックを出力時に分離できるようにする事が可能なので、MDでも手軽に同期音源を作成でき、そのMTR機材の持ち運びもハードディスクMTRのように「移動中にデータが壊れたりしたら・・・」という心配もほとんどないのでMDによる同期はなかなか手軽でオススメです。同期音源の制作自体は私はハードディスクMTRでやっていますが、普段の練習ではMDの左右に分離させた同期音源を使用していますし、これでライブもやりました。 まず、普通のMDの左のチャンネルにベースとシンセなど(まぁ左右逆でもいいが)、 右のチャンネルにクリックを録音し、 自分はクリックをモニターしながら、左のチャンネルのみをダイレクトなりステレオアウトなどから出力するという感じです。 クリックを録音する右側のチャンネルは、録音時、リバーブなどは皆無にしておき(でないと右のチャンネルのクリック音が左のチャンネルに漏れて出力してしまう)、パンは右に完全に振り切ります。 同期音源制作のヒント とりあえず、スタジオ練習での私のドラムの椅子の後ろに簡単にセットしたマイク1本と同期音源をラインでコンパクトミキサーにつないで簡単に録音したものを実際にmp3でアップしてみる事にします。
まぁこんな感じで常にカチカチ鳴っているクリックを聴きながら平気でドラムを叩かなくてはなりません。ポイントは、「同期しているっぽい感じを出さない」事が私のテーマですので、クリックはあくまでガイド的な要素でしかなく、実際に注意して聴く音はクリックというよりベースやシンセですね。 ベース自体もクリックに合わせて自分がレコーディングしたものなので、ベース自体が既にクリックからズレているような同期音源の曲もあるため(笑)、クリックよりもベースに集中してドラムを叩いています。 ライブ感が出るように同期で演奏したい場合は、 同期音源のテンポ自体をあらかじめ揺らしておくという手があります。 上の録音データでも、最後のあたりのドラム乱舞の場所でテンポを違和感のない程度に結構遅くしています。他にも最初のテーマからAメロに移る所やBメロからサビに移るところのフィルインの部分なども若干テンポを遅らせています。 このような同期音源のテンポの意図的な操作は、ライブ感の追及だけでなく、 実際に高速な曲をクリックに合わせてやった事がある人なら解ると思います、 フィルインなどは若干テンポを気持ち落とし勝ちです。モタるとか破綻するとかいう意味ではなく、一定のテンポのままフィルインを叩ききると若干無機質感が漂います。 このように、実際に自分がドラムを叩くときに、レコーディングじゃなかったら若干テンポが遅れるだろうなぁと予想できる場所や逆にハシり勝ちになる(或いはそれが味となる場合)を予想して同期音源をテンポを揺らして制作しておきます。 それによって、体調が優れない時に同期音源に合わせた時に高速フィルインなどで、 「機械が速い…しんどい…(汗笑)」 と思ったりせずに自然な感じでドラムが叩けます。 それが結果的にライブ感を同期でありながらもかもし出すポイントとなると思います。 まぁ同期音源で恐いのはとにかく体調の変化によってテンポを操作できないところです。 体調が悪い時は、速い曲はより一層速く感じますから、「機械が速い・・・待ってくれ!」みたいになりやすいです(笑)。 逆にテンションが上がると、動機音源のテンポが遅く感じてに物足りなさを感じてハシり気味になる場合もあります。そこらへんは色んな意味で完璧を求めるための対策をとろうとするとキリがないですね(笑)。 同期音源のテンポを揺らすというのがもっと解りやすい曲もアップしてみましょう。
まず、聴いていただければ明らかに解るのは、Bメロからサビへ移るところ。 このような曲調のもので、もし、そのままのテンポで淡々とやると、ものすごく単調になってしまい勝ちな部分をあらかじめクリックの作成の時点でテンポを遅くしています。 突然テンポが落ちると不自然なので、徐々に遅くしている感じで制作しており、 その徐々に遅くなる感じが、自分がクリックを聴きながら演奏する際にぎこちなくならないように、クリックの打ち込み方にも工夫をしていますので参考になれば幸いです。 また、気付かなかった人もいるかもですが、AメロからBメロなるとテンポが速くなっています。 もしAメロのテンポのままBメロ(16ビートでハットを刻んでいる場所)にいくと、何故か不思議なことにBメロがトロく感じます。 なので、Bメロのテンポは実はAメロよりも速いのです。 このような曲調では、淡々と機械のような一定のテンポで叩くと聴けたもんじゃないので、同期演奏用の音源制作は難易度が高いかもしれません。 他にもこの曲の中で、別のBメロからサビに移る部分でドラム単体でフィルインが入る部分があるのですが、そこの部分もテンポはかなり遅くクリックを打ち込み、いかにもライブでリアルタイムに演奏しているように聴かせられるようにしています。
ドラム単体のフィルインのところは、他のパートに合わせる必要がないため、 必ずしもクリックにバッチリ合わせなくてもいいので、クリックはあくまでガイドというか目安のものとして、ライブっぽくリズムを揺らして自由なタイム感でフィルインを叩く事が可能です。クリックを使わずに自分の感覚でドラムを叩いた時に自分のドラミングのテンポがどう揺れているかを自分で分析してクリックを打ち込む作業をやるとよいと思います。 つづいて、今度は、ドラムを叩かない空白部分があるような曲の場合の話ですが、、、
この曲はブレイクが多く、同期演奏をする際に、クリックをモニターしているドラマー自身は問題なくても、そのブレイク中にギターは何かリフをやっているような場合、 クリックをモニターしているわけでもないギタリストへの考慮が必要です。まぁ当たり前なのですが(笑)、ドラマー自身がクリックをモニターしていても、ギタリストなどはドラムをアテにリズムを捉えていますから、ブレイクの部分では、ハットを踏むかスティックを叩くなどした方がいいでしょう。上の録音では少し解りにくいかも知れませんが、 ドラムがブレイクするような場所もハットやスティックを叩いてリズムが他のパートに解るようにしています。同期演奏はとにかく機械は待ってくれませんから、フィーリングによってテンポを勝手に変える事ができないため、キメなどは慎重にやらないといけません。 また、そのタイミングをメンバー全員の身体に染み付かせる為に、新曲などに取り掛かる際やリズムがガッチリ合っていないと感じたら、同期音源のベースやシンセだけでなくクリックもアンプなどから出力してメンバー全員がクリックを聴きながら練習すると、正しいタイミングが身体に染み付き、次第にクリックがなくてもブレイクの部分の感覚が身に付くと思うのでいいと思います。 続きまして、変拍子などが混じる曲などの例を一応紹介しておきましょう。
これはAメロの部分が8分の7拍子になっています。 クリックは普通に ピッカッカッカッカッカッカッになっています(謎笑)。 変拍子は人によってどこにアクセントをつけるとかどういうリズムの捉え方をするかが曲などによっても異なるので、 まぁクリックに打ち込み作成は、それによってテキトーに作成します(笑)。 また、この曲は特に解りやすいですが、クリックに対して、ベースがそもそも若干ズレています(笑)。これはベースをレコーディングした私がヘタクソだからであって(笑)、そうなると、同期してドラムを叩く場合に、クリックを聴いてしまってはベースとドラムがズレるので(笑)、クリックはあくまでもガイド的存在で、ベースを集中して聴くべきです(笑)。ちなみにこのテイクは、この新曲に始めて音合わせ練習に取り掛かった日のスタジオ練習を録音したものなのでドラムの演奏もなかなかアヤシイですが(笑)。 同期演奏バンドのライブでの課題をクリアするためのヒント 私が所属しているバンドでは、 ベースが不在の為に、 ベースとシンセとクリックを自分であらかじめレコーディングしたものを同期音源として、(ベースは人間感を出したいので打ち込みではなく私自身がレコーディングしています) ドラマーである私がカチカチ鳴ってるクリックに合わせて演奏しているわけですが、 ライブでの問題として、何か曲が終わった後にリアルタイムでワーッと盛り上がってフリーで時間を横に流して、さいごにミンナで「ジャーーン!」とシメる時、 ベーシストが不在だと同期音源にあわせたようなバンドの場合は、その最後の「ジャーン」のベースの音がない(ギタリストがワーミーでギターでベースの音を奏でることも可能です…)ので、それをどうするかという課題などがあります。 つまり、同期バンドは、ライブの時に、いかに同期っぽくなくライブっぽくできるかがポイントとなると思います。ただ曲を普通に演奏するだけではライブになりにくいので工夫が必要です。 そこで、私が考えた方法を一つここに録音データを交えて紹介しようと思います。
ちょっとこれはMDウォークマンで録音した時のウォークマン側のレックレベルを血迷っていたために音質が悪いですが(笑)、 これはライブでよくラストに持ってきていた曲の最後らへんからです。 録音は、スタジオ練習の時にライブを想定した練習などした時に簡単に軽く録音したものです。 曲が終わった後、フリーの流れでテキトーに音をかき回していますが、 その部分のシンセやベースは、だいたいライブの感じを想定してテキトーにあらかじめ自分が録音してあります。 ほどよい長さまでベースやシンセなどで間を伸ばした同期音源をレコーディングしておき、 次のトラックに(同期音源の再生媒体がMDなどの場合)、最後の一発のジャーンのためのベースとシンセの同期音源トラックを用意しておきます。 フリーで音をかき回す部分の最後のへんは、シンセをフェードアウトさせて、次のトラックへの流れが不自然にならないようにしてあります。 ドラムで暴れまわした最後はタムを上から回してスネアに戻ってゆっくりにしていき、 その時、ゆっくりと一発一発スネアを右手で叩きつつ(最初は交互)、その間に左手に持ってるスティックを右の脇に挟みながら、左手で左手側にある同期音源を次のトラックに進めるボタンを押します(笑)。 そのあと、タイミングをうまく合わせて(自分なりにタイミングを合わせれるように最後の一発のジャーンの為のカウントクリックを入れておきます、カウントがなってる間に脇に挟んだスティックを左手に持ち直し、 「タカタドンっ!」 とお馴染みのシメのフレーズを叩き、 最後の一発の「ジャーン!」を見事に同期音源のベースとシンセとあわせるという技です(笑)。 ライブでこれをやると、見ている人は、同期バンドである事に気付かないと思います。 こういう仕掛けを色々な場所に盛り込めば、ドラマーの努力とアイディア次第で、同期バンドでもライブでのパフォーマンスの幅はいくらでも広がる思います。 そういう意味ではドラマー自身が全体の流れや同期音源の制作を自らプロデュースするのが一番好ましいと思いますね。流れを担っているのはドラマー(或いはボーカル)ですから、同期演奏をする本人がそのタイミングを考えながら同期音源を作るなりするのがいいと思うわけです。 そういう意味でもドラマーにはドラム以外のプロデュース的な能力もある程度必要かなと思います。 と、いうわけで、ドラマーがベースなどの音源に同期して叩くというのは、ギタリストがドラムの打ち込みに同期して弾くのとは比べ物にならないほど難易度が高い事なのですが、 ドラマーで同期演奏を強いられている人は頑張ってください(笑)。
←Top Page |
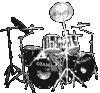
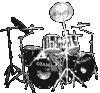
|
Copyright (C) TAKAYA, All rights reserved.